
こんにちは、ますメディアの著者:ふみ(Twitter:@masumediacom)です。
あなたはブログを自分の思うがまま、気分に任せて書いていませんか?
「いい文章を書いているはずなのに、読んでもらえない…」
その理由はいたってシンプルで、読み手が「読みたい」と思える文章を書けていないからです。
ブログを書きたいようにただ書いていては記事を何本書いても、何カ月たっても読者は増えず、記事も最後まで読まれないでしょう。
今回はそんなブログ初心者が陥りがちな過ちを避け、読み手が読みたくなる文章を書くためのテクニックを紹介する内容になっています。
ぜひ最後まで読んで、「読まれないブログ」から「読まれるブログ」になれるように一緒に頑張りましょう!
文章を読んでもらうために必要な3つの視点

まず結論から話すと文章を読んでもらうためには、次の3つのポイントが重要です。
- 感情表現を入れ、自分事化による”共感”を誘発する。
- 伝えたいことがきちんと伝わるよう、”見やすさ”や”わかりやすさ”にこだわる。
- ファーストビュー(冒頭文)で、伝えたいことをまとめる。
では、それぞれのポイントを解説していきます。
感情表現を入れ、自分事化による”共感”を誘発する

共感とは”相手の感情を自分事として感じる事”です。
読み手が共感した文章は読み手にとって自分事となるため、「あ、この文書は私のことをいっているんだ。じゃあ少し読んでみよう」という心理になり、文章を読み進めてもらえるようになります。
ただ、読み手に共感してもらうためにはまずこちらの感情を伝える必要があります。
では、どのように感情を伝えればよいのでしょうか?
感情を伝えるうえで次の2つのポイントが重要となります。
- どこが感情表現なのかが、分かりやすいような演出を行う。
- その感情が誰の感情なのかが伝わるよう、”感情の発信者”をあきらかにする。
例えば感情を表すために「」(カギ括弧)を用いた演出をすることで、その文章は「話し言葉」に見えるため、感情が伝わりやすくなるのです。
この記事の冒頭でも、
「いい文章を書いているはずなのに、読んでもらえない…」
という感情表現を入れることで読み手の共感を誘発し、文章を読み進めてもらおうとしています。(読んでもらえていたら嬉しいな!|ω・) )
また、文末に「!」「?」「….」などの感情を表す記号を使うことでも感情表現はできます。
顔文字なんかも使ってみるとよいでしょう。
そして次に大切なのが”その感情が誰のものなのか”ということです。
感情の発信者の人物像が具体的であればあるほど、その感情の発信者が発する感情は説得性をもち、より深い共感を得ることができます。
ここで次の2つの文章を読み比べてみてください。
パターン①
私は入社3年目の若手社員だ。
今度、取引先との大事な商談がある。
会社にとっては大口案件であり、私にとってはこんなに大きな案件は初めてだ。
「絶対に商談を成功させてやる!」その気持ちで準備している。
パターン②
私は東北出身で就職で上京した入社3年目の若手社員だ。
高校時代、自分の将来の事なんてまるで考えていなかった私は友だちと一緒に地元の大学に進学した。
そして大学生活のなかで何か大きな目標を達成した訳でもなく、ただ毎日を何となく過ごしていた。
気づけば3年がたって就職活動が始まった。
大学時代にとくに目立った活動をしていなかった私は、どこからも内定をもらえず、とにかく面接で落ちまくっていた。
そんな中、なんとか東京の小さなWebマーケティングの企業から内定をもらうことができた。
就職浪人さえ覚悟していた私は、その企業で新卒として働けることになった。
そして私に与えられた職種は営業。
毎日3歳上の先輩と二人で、東京都内にある企業を回った。
基本は飛び込み営業だったので、断られて落ち込むばかりの日々だった。
そんな私を見た先輩は、
「お前っていつも落ち込んでるけど、もっと自分に自信を持ったほうがいいよ。
だって、うちの会社はエントリーした何十人という学生の中からお前を選んだんだよ。
お前がそんなんだったら選ばれなかった他の学生に申し訳なくないか?」
(何十人!?何十社も他の企業からは落とされたのにこの企業は何十人という中から私をえらんでくれたのか。)
私は先輩の言葉に驚いた。
やがて先輩による教育期間が終わり、私は一人で営業することになった。
相変わらず断られてばっかりの飛び込み営業だったが、ある企業から後日プレゼンをする機会をもらった。
そのことを先輩に報告すると、先輩は自分の事のように喜んでくれた。
「よかったじゃねーか!本当によかった。。
プレゼン、頑張れよ!」
先輩は私に熱い言葉をかけてくれた。
そのとき私は思った。
このプレゼンは私一人のプレゼンじゃない。
このプレゼンの成功は今までお世話になった先輩に対する恩返しでもあるんだ。
先輩のためにも、そして自分のためにも今度のプレゼンは失敗するわけにはいかないんだ。
「絶対にプレゼンを成功させる!」
いま私はその気持ちと共に1週間後に迫ったプレゼンの準備をしている。
いかがだったでしょうか?
パターン①に比べてパターン②はかなり長い文章でしたが、おそらくパターン②の方が共感できたのではないでしょうか。
パターン②には共感できる箇所がいくつもあったと思います。
例えば、「私も就活苦しんだなぁ」「飛び込み営業って大変だよなぁ」など共感できたのではないでしょうか。
これら2つのパターンをお見せしたのは、「感情の発信者」に関する情報が具体的になればなるほど、その発信者の感情に共感しやすくなるということを知っていただくためです。
共感を誘うために大切なことは、「感情の発信者」に紐づく「情報」をできるだけ多く伝えることです。
その情報をしっかり伝えれば仮に匿名であっても問題はありません。
また、匿名の強みはありのままの感情をさらけ出しやすいということです。
実名ではさらけ出せないことでも、匿名ならさらけ出せることもたくさんあります。
それによって匿名の方が魅力的な記事になるということは多く見受けられます。
あなたも匿名もしくはペンネームで活動するのもありかもしれませんね。
”見やすさ”や”わかりやすさ”の重要性

文章を読むとき脳には負担がかかります。
なぜなら文章から情報を読み取って頭の中でそれをイメージする必要があるからです。
脳への負担が少ない状態であれば、脳は自由な発想ができるのです。
しかし、脳への負担が大きくなると脳は考えることをやめ、思考が鈍くなってしまいます。
よって文章を作成する際には、読み手の脳に負担をかけないような、見やすく、わかりやすい文章を心がける必要があるのです。
ではそのような文章はどのように書いたら良いのでしょうか?
次の章で解説していきます!
脳は2つの思考で動く

前章で脳への負担を少なくした文章を書く必要があると説明しました。
どんな文章が脳への負担の少ない文章なのでしょうか?
それを知るためには脳はどんな時に負担を感じるのかを知る必要があります。
人間の脳には「システム1」と「システム2」という2つの思考があります。
それぞれ以下のものです。
システム1
物事を直感的に理解しようとする思考。
システム2
物事を論理的に理解しようとする思考。
例えば、綺麗な女優さんが化粧品のCMに出演しているのは、その化粧品を使うことでその女優さんのような美しさを手に入れられるというイメージを視聴者に持ってもらうためです。
これは脳のシステム1を利用したマーケティング戦略といえます。
人間の脳は何かを判断する時に、まずはシステム1の思考を用いて、「これはいい」「これはだめ」というふうに物事を直感的にふるいにかけています。
このような脳の働きを考えると、文章を考える際に注意するべきことが見えてきます。
脳が少しでも「この文章は疲れるな」と判断してしまえば、あなたの文章は途中で読まれなくなってしまうでしょう。
「システム1」と「システム2」の違い

システム2はシステム1の次に待ち構えている思考です。
システム2は物事を慎重かつ冷静に深くとらえようとします。
よって、システム1を考慮した、”見やすい”文章を作ったとしても、その文章が論理的に破綻していれば結局読んでもらえません。
文書を読んでもらうためにシステム1、システム2に配慮するには、それぞれ次のことに気を付ければよいでしょう。
- 心理的負担が下がるくらい、見やすい・読みやすい文章
➡システム1に配慮 - 論理的に理解しやすい文章
➡システム2に配慮
次の章ではシステム1,システム2に配慮するためには、どのような文章を作ったらよいのか解説していきます。
「システム1」に配慮した文章作成のポイント

まずシステム1に配慮するためにはどのようなことに気を付けたらよいのでしょうか?
それは主に次の7つのポイントを抑えるとよいでしょう。
システム1に配慮すべき7つのポイント
- 改行と行間に気を配り、心地よいリズムを意識する
- 漢字とひらがなの含有率を調整する
- 「この」「その」「あの」などの指示代名詞を減らす
- 目次を用いて記事構成を整理する
- 感情表現をいれて自分事化による共感を誘発する
- 文字のサイズや色、強調のルールに気を配る
- 写真やイラストを挿入する
順番に解説していきますね。
1.改行と行間に気を配り、心地よいリズムを意識する

システム1を意識した文章を作るためには、必ず改行と行間には気を配ってください。
改行と行間がない文章は非常に読みづらく、読み進めるのが非常に苦痛です。
改行や行間を取り入れることで、文章に適度な「間」が生まれ、リズムよく読み進めることができるのです。
改行は、「。」「!」「?」などの記号で終わるタイミングでするとよいでしょう。
1文が終わるタイミングで改行することで、常に文章の始まりが左にそろい、画面をスクロールした際に文章を目で追いやすくなります。
ぜひ試してみてください。
2.漢字とひらがなの含有率を調整する

パソコンやスマホで文章を入力していると、普段は使わないような難しい漢字をついつい使ってしまうことがあります。
普段使わないような漢字は読みづらく、脳への負担が大きくなってしまいます。
漢字を使う際には、「その単語は本当に漢字である必要があるのか?」を考えるようにしましょう。
また、漢字が極端に多い記事は、ぱっと見ただけで難解に思えてしまうので、読み手の心理的障壁ができてしまいます。
あえてひらがな表記を採用する場合の基準の一例を以下にまとめます。
ひらがな表記を採用する基準
- ひらがなにしたほうが、読み手の脳の負担が減りそうな場合
- 普段は漢字で書かない言葉を使っている場合
- 常用漢字表に載っていない漢字を使う場合
- 漢字で書いた方がよいか、ひらがなで書いた方がよいかわからない場合
例えば、「敢えて」は「あえて」、「暫く」は「しばらく」と表記した方が読み手にやさしい文章と言えます。
3.「この」「その」「あの」などの指示代名詞をあえて減らす

いま、ネット上の記事をスマホを使って読む人が非常に多いです。
スマホで一気に下までスクロールして、自分の読みたいところだけ読むユーザーも多いです。
そうした場合、「この」「その」などの指示代名詞を多く使っている記事では、読み手は主語が分からず、文章の意図を理解することができなくなってしまいます。
そうしたことを防ぐために「固有名詞」を指す場合は、指示代名詞は使わず、極力「固有名詞」をつかうようにしましょう。
また、指示代名詞を減らし、固有名詞を使うことは検索エンジンも文章の内容を理解しやすくなるため、SEO的にも有利にはたらくと考えられます。
ただし、すべての指示代名詞をなくしてしまうということをやってはいけません。
指示代名詞は文章のリズムをつくる大事な要素ですから、不自然にならない程度に減らすことが大切です。
4.目次を用いて記事構成を整理する

記事が長くなればなるほど、どこに何が書かれているのか分からなくなります。
そこでオススメしたいのが、冒頭に目次を設定することです。
そして、その目次をページ内リンク(目次に該当する内容が書かれている箇所までジャンプするリンク)にすれば読み手はより読みやすくなるでしょう。
5.感情表現をいれて自分事化による共感を誘発する

結論から先に言うと、感情表現を入れるのであれば、できるだけ冒頭に入れることをオススメします。
なぜ文中ではなく、冒頭なのでしょうか?
冒頭で読み手の共感を誘発できれば、読み手はその記事を自分事と感じ、読み進めてもらいやすくなるからです。
ただし、感情表現を入れすぎてしまっても、くどく感じられてしまってはいけないので、感情表現は2~3文にとどめておきましょう。
私の各記事の冒頭でも感情表現を入れているので参考にしてみてください。
6.文字のサイズや色、強調のルールに気を配る

文章を読むということは、文字を目で追うということです。
読みやすさに配慮するのであれば、文字の見やすさにも配慮する必要があるということです。
文字の見やすさは以下の4つのポイントを抑えておくとよいでしょう。
見やすい文字の4つのポイント
- 文字のフォントは見やすいか
- 文字のサイズはちょうどいいか
- 文字の配色には規則性があるか
これらを意識した文字を採用しましょう。
また、文字の配色に関しては、信号機のルールを意識するとよいでしょう。
信号機は日常的に目にするので、その色のルールは私たちの頭に定着しています。
そのルールを用いれば以下のような配色ルールを考えることができます。
| 色 | 協調の意味 |
| 赤 | 否定、禁止、ネガティブな強調 |
| 黄(オレンジ) | 単純な強調 |
| 青 | 肯定、例示 |
7.写真やイラストを挿入する

「百聞は一見に如かず」
記事内で取りあげるテーマによっては、写真やイラストを使った方がイメージをつかみやすいです。
言葉は万能ではありません。
文章だけで説明するのが難しい場合は写真やイラストの使用を検討しましょう。
また、写真やイラストを使う場合、著作権には気を付けなくてはいけません。
そのため写真はフリー素材などを使うようにしましょう。
私のおすすめは”pixabay”というフリー素材ツールです。
2600万種類以上のフリー素材があるので是非活用してみてください。
「システム2」を意識した論理的な文章作成のポイント

ここまででシステム1に配慮した文章の作成の方法を解説してきました。
それではここからはシステム2を意識した文章の作成のポイントを解説していきます。
まず、システム2とは何かからおさらいしておきましょう。
システム2
➡物事を慎重かつゆっくりと論理的に理解しようとする思考。
では、システム2を意識した論理的でわかりやすい文章とはどんなものでしょうか?
論理的でわかりやすい文章とは、読み手がこちらの主張を聞いて「なぜ?」という疑問を抱かなくなった状態にする文章のことです。
そこで、読み手の「なぜ?」をクリアするために重要なことは次の3つです。
- 相手がわからない言葉を使わない
専門的で難しい言葉を使う場合は、その言葉に関する説明を入れましょう。 - 相手が何に対して疑問を持っているのかを察する
読み手が「なぜ?」と感じるであろうポイントには説明を加えましょう。 - 「なぜ?」に対する理由を導くための十分な根拠を持っている
理由を述べるためには、なぜその理由が言えるのかという根拠が必要です。
論理的な文章を構成する3つの要素

論理的な文章は基本的に、「主張」「理由」「根拠」の3つで構成されています。
例えば次のような文章を読んでみてください。
主張
いま、Googleでは検索ユーザーの検索意図を満足させるコンテンツが上位表示されやすい。
理由
なぜなら、Googleは検索ユーザーの利便性を最優先に考えており、検索ユーザーの意図に合ったコンテンツを表示することが、ユーザーの利便性につながるからである。
根拠
事実、いまのGoogleの検索結果を見ると、上位に表示されているページの多くは、検索ユーザーの検索意図を満足させるコンテンツを提供している。
ウェブライダー
沈黙のWebライティング – Webマーケッター ボーンの激闘 – (cpi.ad.jp)
このように、自分の主張を通したいときは「理由」と「根拠」が必要です。
そして、その理由と根拠が多ければ多いほど、その主張は確固たるものになるのです。
相手の反論に先回りして反論しておく

どんな主張にも、それに対峙する意見、”反論”が存在します。
その反論を打ち破らないと、あなたの主張を通すことはできません。
そこでオススメなのが、あらかじめ主張に対する反論を予測し、その反論に対して先回りして答えを用意しておくことです。
広い視野で様々な議論を予測し、それらの議論への対応を考えておくことが求められます。
予測される反論に対する反論を考慮した次の文章をご覧ください。
主張
いま、Googleでは検索ユーザーの検索意図を満足させるコンテンツが上位表示されやすい。
理由
なぜなら、Googleは検索ユーザーの利便性を最優先に考えており、検索ユーザーの意図に合ったコンテンツを表示することが、ユーザーの利便性につながるからである。
根拠
事実、いまのGoogleの検索結果を見ると、上位に表示されているページの多くは、検索ユーザーの検索意図を満足させるコンテンツを提供している。
反論(主張)
いま、Googleでは検索ユーザーの検索意図を満足させるコンテンツが上位表示されにくい。
反論(理由)
なぜなら、Google検索はそもそも検索ユーザーの検索意図を正しく把握できていないからである。
反論(根拠)
事実、いまGoogleの検索結果を見ると、「真田幸村」で上位に表示されるページの中に、「モンスト」というゲームに登場してくる「真田幸村」というキャラクターを紹介しているページがある。
「真田幸村」で検索するユーザーの多くは、ゲームのキャラクターの情報など求めていないはずである。
反論に対する反論(主張)
「真田幸村」で上位に表示されいているページの中に、モンストのキャラクターを紹介しているページがあることこそが、Googleが検索ユーザーの検索意図を正しく把握していることを表している。
反論に対する反論(理由)
なぜなら、モンストは世界累計ダウンロード数3,500万回を超える人気ゲームであり、「真田幸村」と検索する人の中には、モンストの「真田幸村」の情報を求めている人も存在するはずだからである。
反論に対する反論(根拠)
事実、Googleのキーワードプランナーというツールで「真田幸村 モンスト」と調べると、月間検索回数が22,200回とわかる。
「真田幸村」の月間検索回数が30万回なので「真田幸村 モンスト」の検索回数はなかなかの多さであると言えよう。
結論
結局のところ、Googleでは検索ユーザーの検索意図を満足させるコンテンツが上位表示しやすいと言える。
ウェブライダー
沈黙のWebライティング – Webマーケッター ボーンの激闘 – (cpi.ad.jp)
このように、「反論」「反論に対する反論」を用意しておくことで、あなたの主張は力強い説得力を持つことになります。
また、主観的な意見だけではなく、信頼できる筋からの客観的な情報も載せておくことで、より強い主張となります。
セルフディスカッションをする

論理的かつ、読みやすい印象を与える書き方が、「セルフディスカッション」です。
これは、自身が読み手(客観)の視点に立ち、自身の主張に対して「なぜ?」という疑問をぶつけて、自問自答していく書き方です。
セルフディスカッションでは5W3Hを意識して質問を投げかけると、どんどん深堀していけます。
(5W1Hとは、When、Where、Who、Why、What、How、How many、How muchのことを言います。)
セルフディスカッション 例
主張
「免疫力をアップしたければ、腸内細菌を増やすとよい」
A:免疫力を増やしたければ、腸内細菌を増やすといいらしいよ。
B:え、腸内細菌ってなに?
A:腸の中に生息している細菌のことさ。
例えば、乳酸菌とかビフィズス菌とか。
B:乳酸菌やビフィズス菌が増えるとなんで免疫力がアップするの?
A:それは、免疫力をコントロールしている「免疫細胞」が、腸内細菌と戦うことで活性化されるからさ。
B:。。。
A:。。。
続…
このような会話形式の書き方がセルフディスカッションです。
セルフディスカッションには注意点があります。
会話形式にすることで、だらだらとした長い文章になってしまい、読み手をあきらかしてしまう可能性があります。
無駄な文章はカットし、簡潔なわかりやすい文章を心がけましょう。
記事の文章は「結論」➡「理由」の順を徹底する

記事を書く際に重要なのは、結論を先に書くということです。
結論を先に伝えることで、読み手は「なぜそういう結論になるのだろう?」と気になり、先に読み進めてくれます。
ところが、先に結論を述べなければ途端に記事は読まれなくなります。
なぜなら、読み手は、まずその記事に自分の知りたい情報があるのかどうかを知りたいからです。
その記事に自分の知りたい情報があるのかどうか判断できない場合、読み手はすぐに記事から離脱してしまいます。
検索エンジンからやってきたユーザーは、自分の悩みや疑問を解決するための答えを迅速かつ的確に求めています。
このユーザーの行動心理を念頭に置いて記事を作成してください。
ファーストビュー(冒頭文)で、伝えたいことをまとめる

上記の『Webの文章は「結論」➡「理由」の順を徹底する』の章でもお伝えしたように、読み手にとって有益な情報があるのかどうかがすぐにわからない記事からは、読み手は離脱してしまいます。
そのため、ファーストビューで読み手が必要としている情報を可能な限り伝えることが重要です。
以下に、ファーストビューで意識すべき5つのポイントをまとめておきます。
ファーストビューで意識するポイント
- 記事の更新日を記載する
➡ユーザーは新しい情報を求めるため、記事の内容が新しいことを明示する。1~2週間に1度は更新日を改めるとよいでしょう。 - 記事が誰に向けて書かれたものなのかを明示し、読み手の”自分事化”を図る
➡読み手に自分事であると自覚してもらうことで、記事を先に読み進めてもらいやすくなります。 - 記事に書かれている内容を簡潔に要約する
➡ネットで記事を読む人たちは、その記事に自分の欲しい情報があるのかどうかわからないと、すぐに離脱してしまいます。そのため、その記事に何が書かれているのかを冒頭で簡潔に伝えるようにしましょう。 - 記事の内容がわかりやすいように、目次を設定する
➡情報量が多い記事では、どこに何が書かれているのかがわかりません。それを一目でわかるようにするために目次を設定してあげましょう。ユーザーの利便性の向上にもつながります。 - 話者を明らかにし、読み手が書き手の感情に共感しやすい状態をつくる
➡読み手が共感した文章は、読み手にとって自分事となるので、「この記事は自分に関係があるのかも。じゃあ、読んだほうがよさそうだな」と感じ、読み進めてもらいやすくなります。
文章の推敲を行う

記事を書いた後は、必ず何度も読み返し、システム1とシステム2に配慮された文章になっているかを確認してください。
推敲の際には以下の2点を意識するとよいでしょう。
推敲する際の2つのポイント
- 複数の端末でレイアウトが見やすいかを確かめる
- 声に出して読んでみて、強調や行間が適切かを確かめる
また、推敲した結果、部分的に文章に修正を加えることになった場合は、修正後に必ず冒頭から文章を読み直すようにしてください。
なぜなら、部分的に修正すると、記事全体のリズムや論理展開に違和感が生じることがあるからです。
違和感のない、流れるような文章にするためにも、修正後は冒頭から読み直すようにしましょう。
まとめ

いかがだったでしょうか。
ここまで読んでみて、あなたの記事の改善するべき場所が見えたのではないでしょうか?
今回の記事で文章作成のポイントをいろいろと述べましたが、要点をひとことでまとめると、「ユーザーの利便性を最優先に考えたコンテンツを作成する」ということです。
コンテンツの質の良し悪しは、ユーザーの反応に正直に表れます。
ユーザーが求める情報を正確に、かつ迅速に提供し、ユーザビリティを追求したコンテンツを目指して文章を書けば、おのずと結果はついてきます。
めげずにブログの作成、頑張ってください!
最後に、私のブログでは、ブログの作成のコツに関する記事を投稿していますので、ぜひあなたのブログ作成にお役立てください。
(ブログの書き方・ノウハウ徹底解説!!最初の記事はこう作る!)
著:ふみ
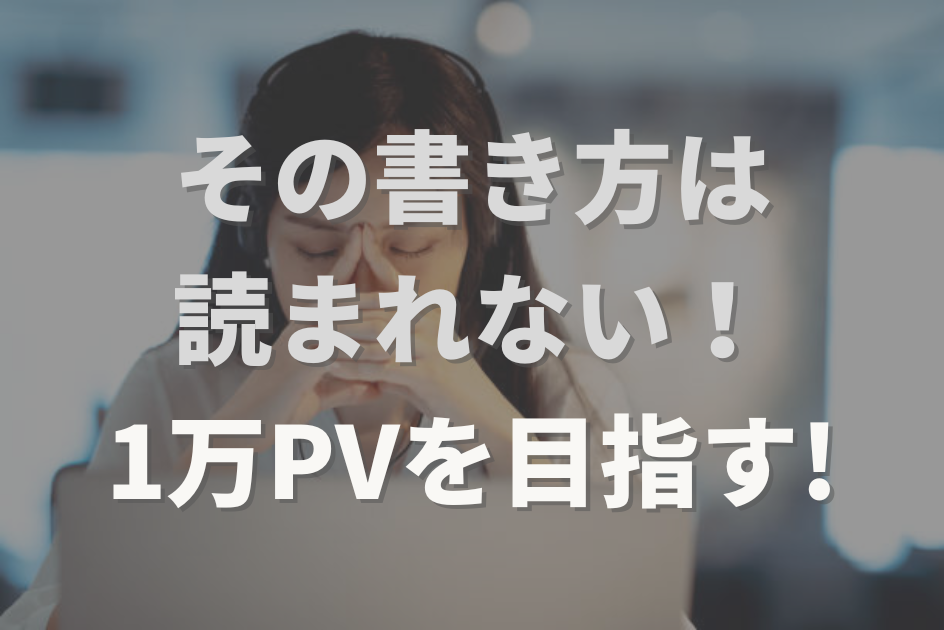
コメント